就活の軸とは?考え方や面接の答え方の例文5つを紹介!

就職活動をしていると、一度は耳にしたことがあるであろう「就活の軸」という言葉。
しかし、中には、
 就活くん
就活くん「そんなに大切なものなの?」
と疑問に思われている方もいるのではないでしょうか。
結論からいうと就活の軸は就活の方向性を導き出すために極めて重要で、ここが曖昧だと必ず失敗します。
そこで本記事では就活の軸とは何か、どうやって決めるのかといったポイントを紹介していきます。
就活の軸とは?必要な理由も紹介


就活の軸とはそもそも何なのか。
まずは、就活の軸についての基本事項からご紹介していきます。
そもそも就活の軸とは?
「就活の軸」とは、仕事選びや企業選びをする際の自分なりの価値観や判断基準のことです。
大きく以下の2種類に分かれます。
- 自分に関する就活の軸
例:「こんなキャリアを積んでいきたい」など
- 自分以外(業界や企業など)に関する就活の軸
例:「グローバルに活躍できる環境が欲しい」など
まずは両軸でピックアップしていきますが、数が多すぎると逆に定まらないので、譲れないものに絞りましょう。



就活の軸を企業が気にする理由
就活の軸はESや面接でもよく聞かれますが、それはなぜでしょうか。
その答えはズバリ「学生側が求めるキャリアビジョンや企業像(≒就活の軸)と、企業側の実態とが一致しているかを確認するため」です。
軸と合っていない企業に入社してしまうと、ミスマッチと気づき辞めてしまうことも少なくありません。
例えばよくある例でいうと以下のようなものがあります。
- ガツガツ働きたいのに、のんびりした会社で成長機会が少ない
- 裁量をもって仕事がしたいのに、大手だから裁量があまりない
このようなミスマッチは学生も企業も両方が不幸になるので、それを確認し、合わなければ落とす理由となるのです。



就活の軸を決めるメリット


企業側からも問われることが多い就活の軸。就活の軸は、就活を進めていくうえで、大変重要な役割を担ってくれます。
就活の軸を設定することで得られるメリットを2つご紹介しましょう。
志望企業が明確になる
1つ目のメリットは「志望企業が明確になる」ことです。
就活の軸を決めると、「自分のやりたい仕事が明確になる→それができる業界・仕事が見つかる」というように明確化します。
軸に合っていない企業を自動的に弾けるので、的を絞って効率的に就活が行えるのです。



面接での受け答えに悩まなくなる
2つ目のメリットは面接の受け答えに悩まなくなることです。
「就活の軸は何ですか?」という問いに答えられるのはもちろん、志望動機、ビジョン、強み・弱みなど全ての問において軸があるから、一貫した答えが言えるのです。
矛盾した答えがあると支離滅裂だと思われるか、「結局どういうこと?」と聞かれて答えに詰まるかのいずれかでしょう。



就活の軸の考え方を3つ紹介


ここからは就活の軸の考え方を紹介します。
自己分析
まずは自己分析で自分に何が興味があり、何ができるのか、強み・弱み、好き・嫌いは何なのかを洗い出しましょう。
就活の軸は全て「◯◯したい」というものでもなく、「苦手・嫌いなことをやらない」という軸を設けてもいいでしょう。



また、「サッカーが好き」と言っても、チームプレーが好きなのか、戦略を立てるのが好きなのか、分析をするのが好きなのかと様々ですので、「◯◯で◯◯するのが好き・得意」と動詞ベースで考えましょう。
インターンや会社説明会に参加
自己分析で興味のある業界・企業が見えてきたら、それらのインターンや会社説明会に参加しましょう。
実際に参加してみて、「なんとなく、ここのインターン楽しめたし、好印象!」「ここは、そんなに面白くなかった」と気付きがあるはずです。
そこで、なぜあなたがそう感じるのかを言語化していきましょう。
実際に体験することで、「自分に合うと思ったものが現場だと合わない」と気付き、就活の軸の軌道修正につながりますよ。



優先順位をつける
気になった企業が複数あれば、それらを比較してみましょう。
異なる業界の企業を比べて、どっちの方がなぜ良いと思ったのかを深堀りします。
例えば「A社の雰囲気は好きだけど商品にあまり興味がないから、B社の方が好印象」というように、より言語化できていくでしょう。



業界別の就活の軸の事例・例文一覧
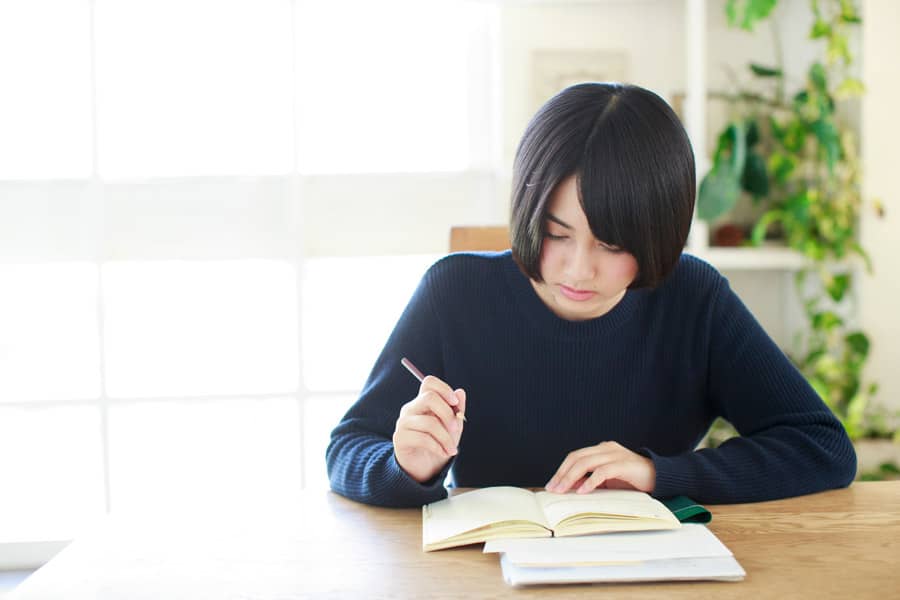
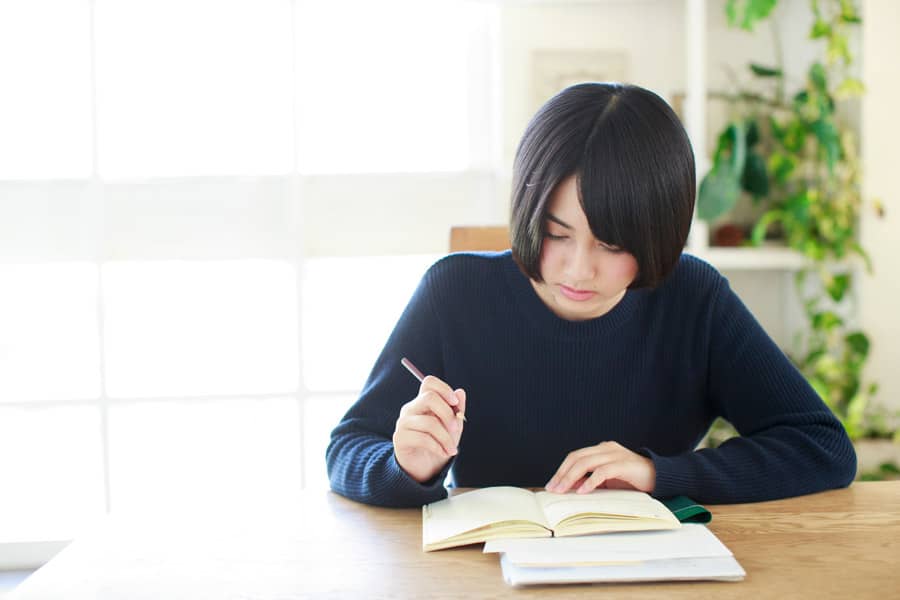
ここからは業界ごとの就活軸の具体例を見ていきましょう。
例文1:金融業界
銀行(信用金庫)志望の例文
私は生まれ育った●●県が大好きで、「●●県をもっと元気にしたい」という軸のもと、就活を行っています。
そして、●●県を元気にするには、●●県の経済基盤となっている中小企業を支援し、活性化させることが不可欠であるという考えから、それを実現できる信用金庫への就職を志望しています。
私には、よく足を運んでいるお気に入りの飲食店があります。中年のご夫婦が経営されているのですが、数年前「経営が苦しくて、店をたたむことも考えている」とおっしゃっていた時期がありました。しかし、金融機関から融資を受け、店舗やメニューのリニューアルを行ったことで、売り上げが回復し、今では多くの人々の憩いの場となっています。
金融機関からの融資は、経営者であるご夫婦の仕事を守り、私を含む多数の顧客をハッピーにしてくれました。この経験から、金融機関、とりわけ地域と強いパイプのある信用金庫に就職し、中小企業を支援することで、●●県に住む人々を笑顔にし、県全体を元気にしたいと強く思うようになりました。
保険会社(生命保険会社)志望の例文
私の就活の軸は「人の一生に寄り添う仕事がしたい」というもので、それを実現できるのが生命保険会社だと考えております。
数年前、一家の大黒柱である父に癌が見つかりました。幸いなことに生命保険に加入していたため、お金を気にせず治療を受けることができ、今は元気に生活していますが、もし生命保険に加入していなかったら、どうなっていたか分かりません。また、闘病中に父が言っていた「もしお父さんが死んでも、保険金がおりるから、お金の心配はいらないぞ。お前たちは何も気にせず好きなことをやれよ。」という言葉が非常に重く心に残っています。
この経験から、「いざというときも、人々が安定した生活を営めるようサポートをする」という生命保険の役割の重要性を学んだと共に、私もこの仕事に携わり、お客様の一生に寄り添いたいと思うようになりました。
例文2:商社志望
総合商社志望の例文
私は「人々の生活を豊かにしたい」という軸のもと、就活を行っています。そして、数ある業界の中でも、特に商社に魅力を感じている理由は、日本の人々だけでなく、世界中の人々の生活を豊かにする可能性を秘めているからです。
私は途上国である●●国に留学経験があります。約1年という期間でしたが、商社が展開するビジネスによって、人々の生活が便利で豊かなものに変わっていく様子をこの目で見ました。これは、決まったモノを作るのではなく、頭と情報を駆使し、現地の状況に応じたビジネスを自由に展開することができる商社だからこそ実現できるものだと考えております。
このような経験から、私も商社に入社して、国内に限らず世界中の人々の生活を豊かにする仕事に携わりたいと思うようになりました。留学生活によって培った英語力や適応力も、商社での仕事に大いに活かせるものと考えております。
専門商社(食品)志望の例文
私は食べることが大好きで「食に関わる仕事がしたい」という就活の軸を持っています。その中で、農業でもなく食品メーカーでもなく商社を志望した理由は、「自社で生産・製造した商品だけでなく、世の中に出回っている全ての商品に携わることができるから」です。
私は10か国以上の国々を旅行した経験があります。日本の味が恋しくなったとき、現地のコンビニやスーパーに日本製のお菓子やカップラーメンが売られていたときの喜びといったら、口では言い表せないほどです。逆に、海外で美味しいと思った商品を日本国内の売り場で見かけたときも、とても嬉しい気持ちになります。
このように、消費者が求める商品を購入できる環境を創るためには、メーカーと小売業者の架け橋とも言える、商社の働きが不可欠です。入社することが叶ったら、生産国やメーカーという枠に囚われることなく、様々な商品の流通に携わり、消費者の元へ”美味しい”を届ける一助を担いたいと考えております。
例文3:人材業界
私の就活の軸は「人生をより良くしたいという人に寄り添い、最良の答えを出すためのサポートがしたい」というもので、人材業界を志すようになりました。
そのような軸を持つようになったきっかけは、大学時代を通して力を入れていた塾講師のアルバイトです。塾では、授業だけでなく、中学生や高校生の進路相談を受けることが多々ありました。中でも印象に残っているのが、国立大学と私立大学に合格し、どちらに進学するか迷っていた生徒です。
私は、その生徒の成績や性格、そして将来の夢などを加味しながらマンツーマンでじっくりアドバイスをしました。その生徒は最終的に私立大学を選んだのですが、半年後、塾に顔を出してくれ、「毎日とても充実している。この大学を選んで良かった。先生のおかげです。」という言葉を私にかけてくれました。
この経験から私は、相手の状況を踏まえながら「今」と「未来」を繋ぐサポートをすることにやりがいを感じるようになりました。入社が叶ったら、求職者の希望をしっかり汲み取り、最適な仕事を紹介することで、その人を幸せにするお手伝いをしたいと考えております。
例文4:サービス業界
私は「人の笑顔が見られる仕事がしたい」という軸を持ち、就活をしております。人を幸せにできる仕事はたくさんありますが、人を幸せにしたうえで、笑顔を直接見ることができるのは、サービス業界ならではと思い、この業界を目指すようになりました。
私は「常に笑顔で・誰よりも親切に」をモットーに、カフェでアルバイトをしております。ある日、いつも仕事前に来店される常連のお客様がとびきりの笑顔で「君の接客は本当に気持ちいいね!いつも朝から元気をもらっているよ!」というお褒めの言葉をかけて下さいました。その経験から、私はこのアルバイトをやっていて良かったと改めて実感したと共に、これからもっと多くのお客様を笑顔にしたいと思うようになりました。
入社が叶ったら、アルバイトで培ったホスピタリティを活かし、たくさんのお客様を笑顔にできるよう尽力したいと考えております。
例文5:広告業界
私は大学でデザイン学科を専攻していたことから、「デザインに携わる仕事がしたい」という就活の軸を持っています。中でも広告業界に興味を持った理由は、人々に有益な情報をもたらせる広告というツールをデザインできることにやりがいを感じたからです。
実際、大学では広告デザインの研究や実験製作なども行った経験があり、人々の記憶に定着する広告を作ることの難しさを実感しました。しかし、色彩の勉強をしてデザインをより際立たせるなど、様々な工夫を施したところ、最終的には学内で行われた「POPコンテスト」で見事金賞を獲得することができました。自分が努力して作った広告が、人々に優れた商品や楽しいイベントを知らせるキッカケになること以上に嬉しいことは無いと実感したのはこの時です。
入社後も、技術を向上させると共に、最新のトレンドを取り入れるなど、「より良い広告を作る」という意識を常に絶やさず、人々に感動とインパクトを与えられるような広告作りに励みたいと思います。















